●【米国市況】S&P500が最高値、小売売上高の堅調で-短期債に売り
17日の米株式相場は続伸。S&P500種株価指数は過去最高値を更新した。堅調な小売売上高に加え、失業保険申請件数が減少したことから、景気敏感株を中心に買いが膨らんだ。
小型株で構成されるラッセル2000指数は1.2%上昇。ハイテク株も高い。半導体の受託生産大手、台湾積体電路製造(TSMC)が売上高見通しを上方修正し、世界的な人工知能(AI)投資の勢いに対する投資家の自信を高めた。通常取引終了後にネットフリックスが発表した決算は予想を上回り、同社は売上高見通しを引き上げた。
6月の小売売上高は急減していた前月から幅広い分野で回復。個人消費の減速懸念をやや和らげる可能性がある。先週の新規失業保険申請件数は5週連続で減少し、4月半ば以来の低水準となった。雇用市場の強さが示された。
ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏は「景気が拡大を続け、失業率が低水準を維持する限り、個人消費は続く。この好循環はより高い利益を生み出し続ける可能性があり、株式相場上昇を後押しする原動力になる」と述べた。
ハリス・フィナンシャル・グループのジェイミー・コックス氏は、消費者は4月の関税ショックを乗り越え、消費活動を再開しているようだと指摘。「あとは連邦準備制度理事会(FRB)が9月の利下げサイクル再開方針を明確に示せるだけの、十分なインフレデータがそろうか確認する必要があるだけだ」と語った。
●米小売売上高、6月は幅広く回復-消費減速懸念和らぐ可能性も
6月の米小売売上高は急減していた前月から幅広い分野で回復した。個人消費の減速懸念をやや和らげる可能性がある。
13の業種うち、10業種で増加した。2カ月連続で減少していた自動車売上高が持ち直し、全体を押し上げた。6月の自動車販売台数は減少し、直近インフレ統計では新車・中古車の価格がともに下落した。そのため自動車は小売売上高全体を押し下げるとエコノミストはみていた。
同統計で唯一のサービス項目である飲食店は0.6%伸びた。
今回の統計は、個人消費の健全性を巡る懸念が高まる中で、一定の安心材料となる。関税によって長引く生活費の高騰がさらに悪化するとの懸念は根強く、米国民は今年に入り、景気や家計の見通しに対して総じて悲観的だ。ただ、足元では消費者信頼感に回復の兆しも出ている。
ネイビー・フェデラル・クレジット・ユニオンのチーフエコノミスト、ヘザー・ロング氏は「関税や値上げリスクに対する不安は依然くすぶっているが、消費者はお得だと感じれば購入に動いている」と指摘。「今夏の経済を表現するなら底堅さだ」と述べた。
持ち直しの背景には、トランプ大統領が関税を一部後退させたことがある。だが、足元では主要貿易相手国・地域に対する上乗せ関税やセクター別関税の発動をちらつかせて再び圧力を強めている。さらに直近のインフレ統計では、玩具や家電など関税の影響を受けやすい商品に値上がりの兆候が出ており、輸入コストの増大分が消費者に転嫁されつつあることが示唆された。
国内総生産(GDP)の算出に使用される飲食店と自動車ディーラー、建設資材店、ガソリンスタンドを除いたコア売上高(コントロールグループ)は0.5%増加。堅調な上期の締めくくりとなった。
小売売上高は主に財の購入を反映しており、これは個人消費全体の約3分の1を占める。6月の個人消費支出(PCE)は7月31日に発表される予定だ。この統計では、財・サービスに関するインフレ調整後の支出が示される。
小売売上高統計はインフレ調整前のデータであるため、仮に減少していても、実際の消費が減ったのか、単に価格が下がっただけなのかは判断できない。逆に増加しても、それが販売数量の増加なのか、価格上昇によるものなのか見極めが困難な点には留意が必要だ。
●米新規失業保険申請件数、5週連続で減少-雇用市場の底堅さ示す
先週の米新規失業保険申請件数は5週連続で減少し、4月半ば以来の低水準となった。雇用市場の強さが示された。
失業保険申請件数は5月と6月に増加傾向となった後、コロナ禍前の落ち着いた水準に戻っている。一方、継続受給者数は2021年以来の高水準近くで推移しており、雇用のペースが鈍化する中で、失業者の再就職が引き続き難しいことが示唆される。
●消費者物価は7カ月連続で3%台、伸び鈍化も日銀利上げ路線の支えに
6月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、7カ月連続で3%台となった。エネルギー価格が押し下げ要因となり、前年比の伸びは4カ月ぶりに鈍化したが、日本銀行が堅持する利上げ路線を支える内容と言える。
総務省の18日の発表によると、コアCPIは前年比3.3%上昇と、2013年1月以来の高水準だった5月の3.7%から伸びが縮小した。日銀目標の2%を上回るのは39カ月連続となる。
電気代やガソリンなどのエネルギーは、資源価格の下落などで2.9%上昇と伸びが鈍化した。一方、大手通信会社のプラン変更で携帯電話通信料が11.9%上昇と押し上げに寄与。生鮮食品を除く食料は8.2%上昇と23年9月以来の高い伸びとなった。コメは100.2%上昇と23カ月ぶりに前月の伸びを下回った。前月まで8カ月連続で過去最高を更新していた。
生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.4%上昇と6カ月連続で伸びが拡大し、市場予想(3.3%上昇)を上回った。3%台は3カ月連続。総合指数は3.3%上昇と伸びが縮小した。
●円は148円台半ば、ウォラーFRB理事発言でドル売り-参院選待ち
18日朝の外国為替市場で円相場は1ドル=148円台半ばで推移している。ウォラー米連邦準備制度理事会(FRB)理事が今月の利下げを主張し、ドル売りがやや優勢だ。
あおぞら銀行の諸我晃チーフマーケットストラテジストはドル・円について、6月の小売売上高は強かったものの米金利が上昇せず伸び悩んだところにウォラー氏の発言で下げたと指摘した。
また、加藤財務相が為替動向に触れる発言をしてドルの上を攻めにくいほか、全国消費者物価指数(CPI)は高止まりで日本銀行が利上げしやすい環境にあり、ドル・円相場の重しになっているとした。
20日投開票の参院選で、自民、公明の連立与党の非改選を含めた議席数が過半数(125議席)を下回る可能性が報じられている。大幅に割り込めば石破茂首相の求心力はさらに低下し、政権は正念場を迎える。
三菱UFJ信託銀行資金為替部マーケット営業課の酒井基成課長は、市場で織り込んでいるのは与党の過半数割れで、週明けの外為市場では結果を見てポジションを取るので、日本が休場の21日に大きく動くことが考えられると指摘。「今週見られた財政懸念から悪い金利上昇による円売りがクライマックスを迎えるので、きょうは様子見だろう」と述べた。
投資歴35年の独自メソッドを大公開【成長株投資術体験セミナー】

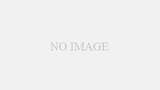
コメント